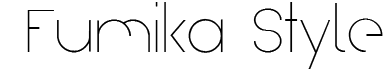ばうばうとした野原に立つて口笛をふいてみても
もう永遠に空想の娘らは来やしない。
なみだによごれためるとんのずぼんをはいて
私は日傭人のやうに歩いてゐる。
ああもう希望もない 名誉もない 未来もない。
さうしてとりかへしのつかない悔恨ばかりが
野鼠のやうに走つて行つた。
萩原朔太郎といふ詩人は、もうすでに此世にはないけれども、此様な詩が残つてゐる。
専造は、大学のなかの、銀杏並木の下をゆつくりと歩きながら、
この詩人の「宿命」といふ本の頁をめくつてゐた。
約束の時間を十分も過ぎたが、五郎の姿はみえない。繁つた、銀杏の大樹はまるで緑のトンネル。
枝々が両側からかぶりあつて、馥郁とした涼風をただよはせてゐる。
この日頃、胃の腑[#「腑」は底本では「附」]の恰好なぞ、考へたこともないほど、
専造は食事らしい食事はしてゐない。
下宿代は滞り勝ち。——二三、友人にあたつてみた職業も、みんな向うから、閉め出しだと云ふ報告。
その上、五郎という厄介な子供を抱へてゐては、宛然、もう水の上の捨て小舟。
といつて、その二、三の友人すら、現在のやうな世の中では、自身の体のなりゆきに、
肝胆を砕いてゐるのがせいいつぱいである。